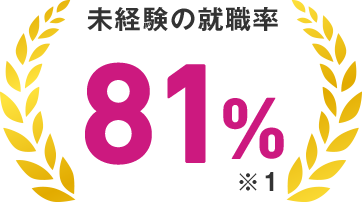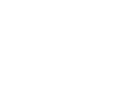【民法の基礎】相続って何だろう?(2)【単純承認、限定承認、相続放棄】
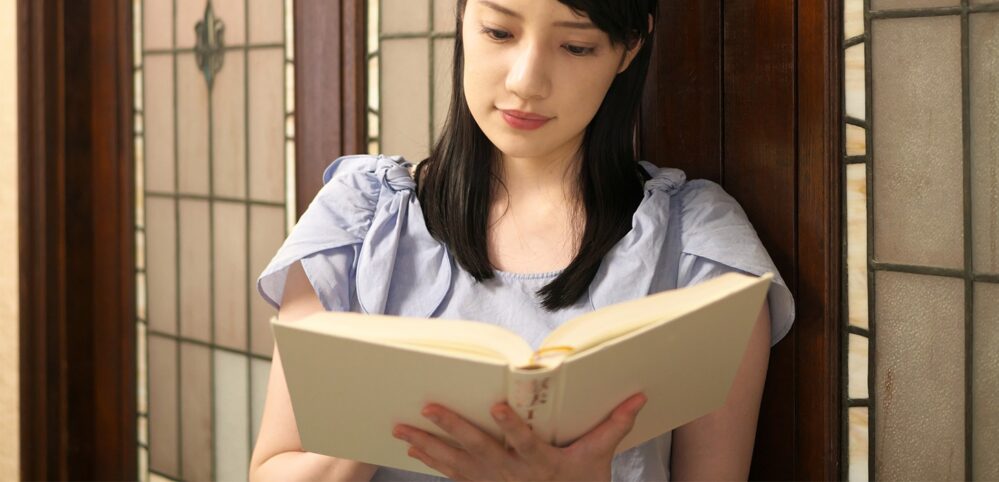
民法は、被相続人の死亡という事実によって
当然に相続が発生することを原則としていますが、
マイナスの資産も相続財産に含まれることを考えると、
勝手に財産を無限に継がされてしまっては
相続人はたまったもんじゃありませんよね。
そこで民法は、相続人の意思を尊重するために、
一定期間内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」
いずれにするかを選択できるようにしています(民法915条1項)。
そこで、今回は、「単純承認」「限定承認」
「相続放棄」について見て参りましょう。
基本は単純承認
相続は、被相続人の死亡によって当然に効力が発生します。
従って、相続人が相続開始の事実を知ったかどうかや、
相続する意思があるかどうかには全く関係なく、
被相続人の死亡と同時に直ちに
相続財産が相続人に帰属します(民法896条)。
原則通りにいけば、
相続人は特に何らの「承継する」との意思表示を要さずに
被相続人の相続財産をまるっと承継することになります(単純承認)。
単純承認の場合、相続人は、
無限に被相続人の権利・義務を承継します(民法920条)。
相続放棄
相続人は、「自己のために相続の開始があったことを
知った時」から3ヶ月以内の熟慮期間内であれば、
相続を放棄することができます(民法915条1項本文)。
なお、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、
- 相続開始の原因事実(被相続人の死亡など)
- 自分が相続人になったこと
の両方を知ったことを意味します。
「相続したくない!」と思った場合、相続人は、
3ヶ月の熟慮期間内に、家庭裁判所に放棄の申述(民法938条)をし、
家庭裁判所が申述を受理する審判をすれば、
最初から相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。
※参考:「みなす」と「推定する」の違いについて知っておこう!
限定承認
相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ
被相続人のマイナスの資産を相続する旨の意思表示を
限定承認といいます(民法922条)。
限定承認は、一見合理的な制度のように思われますが、
実際使われることはほとんどありません。
なぜなら、限定承認をするには、
熟慮期間内に、財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、
さらに申述をする必要があり、しかも、
すべての相続人や包括遺贈者共同して行わなければならず、
大変面倒臭いうえに費用もかかる制度だからです
(民法915条1項、924条、923条)。
法定単純承認
たとえ「放棄したい!」「限定承認したい!」と思っていても、
民法の定める一定の事由が存在した場合には、
単純承認したものとみなされます(法定単純承認,民法921条)。
- 相続財産の一部または全部の処分(1号)
- 熟慮期間である3ヶ月の経過(2号)
- 隠匿、消費、詐害など、債権者に対する背信行為(3号)
1号については、相続人に、相続財産を相続する意思が
黙示的に認められるため、法定承認事由とされています。
3号については、背信行為を行った相続人の保護よりも、
債権者の保護のほうを優先する必要があるからです。
相続が発生した場合は、3ヶ月の熟慮期間内に
放棄などの手続きをとらなければ単純承認したものと
みなされますので、パラリーガルとしては、
より迅速に弁護士をサポートする必要があります。
「自分はパラリーガルに向いているのか?」「最短でスキルの高いパラリーガルになるためには何をしたらいいのか?」などパラリーガル適職診断やパラリーガルとして効率良くスキルを上げる方法が全てわかかる動画を公開しています。
ぜひご活用ください!
↓↓↓ 公式LINEはこちら ↓↓↓


AG法律アカデミー
最新記事 by AG法律アカデミー (全て見る)
- 事務職におすすめの人気の資格ランキング10選!実務に役立つ資格を厳選 - 2025年12月8日
- 事務職のキャリアプラン設計方法とは?5年・10年先の立て方とメリット - 2025年12月6日
- パラリーガルの法律事務で「赤い本」「青い本」といえば? - 2025年11月23日